
後継者問題や事業の未来に悩む経営者の皆様へ。
本記事では、事業承継の有力な選択肢であるM&Aと事業譲渡について、その基本から具体的な手続き、成功の秘訣までを網羅的に解説します。
親族内承継や従業員承継と比較し、M&A・事業譲渡のメリット・デメリット、企業価値を最大化する戦略、税務・法務リスク対策、そしてM&A後の統合(PMI)まで、スムーズな事業承継を実現するために必要な知識が手に入ります。
この記事を読めば、あなたの事業を次世代へ繋ぎ、さらに発展させるための具体的な道筋が見えてくるでしょう。
事業承継の選択肢としてのM&Aと事業譲渡

日本の中小企業経営者の高齢化が進む中、事業承継は喫緊の課題となっています。後継者不足に直面し、やむなく廃業を選択する企業も少なくありません。
しかし、廃業は長年培ってきた技術やノウハウ、雇用を失うだけでなく、地域経済にも大きな影響を与えます。このような状況において、M&A(企業の合併・買収)や事業譲渡は、事業を次世代に引き継ぎ、さらに発展させるための有力な選択肢として注目を集めています。
M&Aや事業譲渡は、単に会社を売却したり買収したりするだけでなく、売り手側にとっては、経営者の引退後の生活設計、従業員の雇用維持、そして買い手側にとっては、事業の持続的な成長を実現するための戦略的な手段となり得ます。
従来の親族内承継や従業員承継が困難な場合でも、外部の企業に事業を引き継ぐことで、経営資源の有効活用と新たな価値創造の可能性が広がります。
なぜ今M&A・事業譲渡が注目されるのか
現代においてM&Aや事業譲渡が事業承継の手段として注目される背景には、いくつかの重要な要因があります。
最も大きな理由の一つは、多くの中小企業が直面している深刻な後継者不足問題です。少子高齢化が進む日本では、親族内に後継者がいない、あるいはいても経営能力や意欲に課題があるケースが増加しています。経営者に、事業を継続したいという強い思いがあっても、選択肢が見つからずに廃業を余儀なくされる企業が後を絶ちません。
M&Aや事業譲渡は、こうした後継者問題に対する有効な解決策となります。外部の企業に事業を譲り渡すことで、経営者は事業の継続と発展を託すことができ、従業員の雇用も守られます。また、経営者自身は事業売却によって創業者利益を得ることができ、引退後の生活資金を確保する上でも大きなメリットとなります。
さらに、M&Aは企業の成長戦略としても活用されています。買い手側にとっては、既存事業とのシナジー効果を追求したり、新規事業への参入を加速させたり、市場シェアを拡大したりするための有効な手段です。売り手側も、大手企業の傘下に入ることで、資金力や販路、技術などの経営資源を活用し、単独では実現が難しかった事業のさらなる成長を目指すことができます。
このように、M&Aや事業譲渡は、単なる事業承継の枠を超え、企業価値の向上と持続的な発展を可能にする経営戦略として広く認識されています。
親族内承継や従業員承継との比較
事業承継の方法には、主に「親族内承継」「従業員承継」「M&A・事業譲渡」の3つの選択肢があります。それぞれの方法にはメリットとデメリットがあり、自社の状況や経営者の意向に応じて最適な方法を選ぶことが重要です。
親族内承継は、経営者の子や孫など、親族に事業を引き継ぐ伝統的な方法です。最大のメリットは、経営理念や社風が維持されやすく、社内外からの受け入れもスムーズに進みやすい点にあります。しかし、親族内に適切な後継者がいない、あるいは後継者候補に経営能力や意欲が不足しているといった問題に直面することが少なくありません。また、相続税や贈与税の負担も大きな課題となることがあります。
従業員承継は、役員や従業員の中から後継者を選び、事業を引き継がせる方法です。MBO(マネジメント・バイアウト)などが代表的です。長年会社を支えてきた従業員が後継者となるため、事業内容や社内の状況を熟知しており、従業員のモチベーション維持にも繋がりやすいというメリットがあります。一方で、後継者となる従業員に事業買収のための資金調達能力が不足しているケースが多く、個人保証の問題や、経営者としての資質育成に時間がかかるというデメリットも存在します。
これに対し、M&Aや事業譲渡は、親族や社内に後継者がいない場合に、外部の企業に事業を引き継ぐことで、後継者問題を根本的に解決できる点が大きな特徴です。買い手企業は、豊富な資金力や経営ノウハウ、販路などを持ち合わせていることが多く、譲渡された事業はそれらの資源を活用してさらなる成長が期待できます。また、経営者は事業売却によってまとまった資金を得ることができ、引退後の生活を豊かにすることが可能です。従業員にとっても、雇用の維持だけでなく、より安定した経営基盤やキャリアアップの機会が提供される可能性があります。
M&Aや事業譲渡は、親族内承継や従業員承継に比べて、より幅広い選択肢から最適なパートナーを見つけることができるため、事業の継続性や発展性、そして経営者自身の利益を最大化する上で非常に有効な手段となり得るのです。
M&Aと事業譲渡の基本構造と法的側面
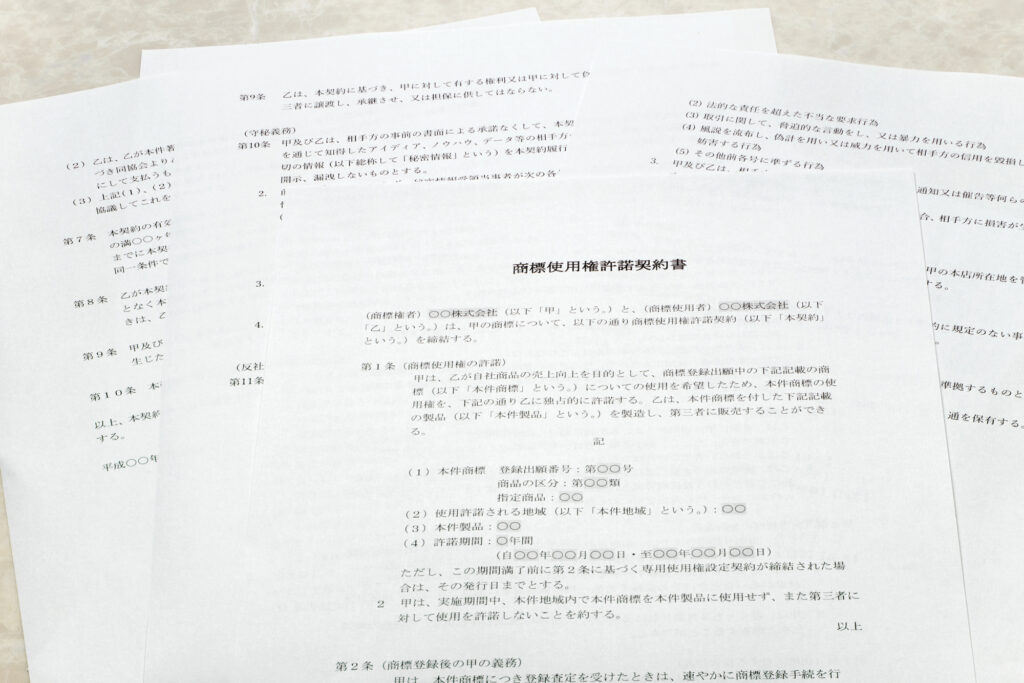
事業譲渡の法的定義と特徴
事業譲渡とは、会社法に定められたM&Aの手法の一つであり、会社がその事業の全部または一部を他の会社に譲渡することを指します。これは、会社そのものを売買する株式譲渡とは異なり、特定の事業部門やそれに付随する資産、負債、契約などを個別に選別して譲渡する「個別承継」の形態を取る点が最大の特徴です。
具体的には、譲渡会社(売り手)と譲受会社(買い手)の間で事業譲渡契約を締結し、対象となる事業に属する土地、建物、機械設備、在庫、取引先との契約、従業員との雇用契約などを個別に引き継ぐ手続きを行います。このため、譲渡対象を柔軟に選択できるメリットがある一方で、個々の資産や契約ごとに移転手続きが必要となるため、手続きが煩雑になる傾向があります。
法的な側面では、原則として株主総会の特別決議が必要とされますが、譲渡する事業の規模や譲受する事業の規模によっては不要な場合もあります。また、譲渡会社には、原則として同一の事業区域内で20年間、譲渡した事業と同一の事業を行ってはならないという競業避止義務が会社法で定められています。
M&Aの種類と事業譲渡の位置づけ
M&A(Mergers & Acquisitions)とは、企業の合併や買収の総称であり、事業承継や企業成長戦略の選択肢として広く用いられます。M&Aには様々な手法があり、事業譲渡はその中でも特定の目的や状況において有効な手段として位置づけられます。
主なM&Aの手法としては、以下のものがあります。
- 株式譲渡:会社の株式を売買することで、会社の経営権を移転する最も一般的な手法です。会社そのものが買い手に引き継がれるため、許認可や契約関係は原則としてそのまま継続されます。
- 事業譲渡:先述した通り、特定の事業部門や資産・負債を選別して譲渡する手法です。なお個人事業主の事業を承継する場合には事業譲渡になります。
- 会社分割:会社のある事業部門を切り離し、新しい会社として独立させたり、既存の他の会社に承継させたりする手法です。包括承継の側面を持ちながら、特定の事業を移転できる点が特徴です。
- 合併:複数の会社が一つの会社になる手法です。吸収合併と新設合併の2種類があります。
- 第三者割当増資:特定の第三者に対して新株を発行し、資金調達を行うとともに、経営権の一部を譲渡する手法です。
これらのM&A手法の中で、事業譲渡は特に「不採算事業の切り離し」「特定の事業部門のみを売却・買収したい」「会社全体のリスクを負いたくない」といった場合に選択されることが多いです。事業承継の文脈では、後継者が特定の事業のみを引き継ぎたい場合や、複数の事業を持つ会社の一部を売却して事業承継資金を確保したい場合などに有効な選択肢となります。
それぞれのメリット・デメリットを比較
M&Aの代表的な手法である株式譲渡と事業譲渡は、それぞれ異なるメリットとデメリットを持ちます。事業承継の目的や状況に応じて、最適な手法を選択することが重要です。
事業譲渡のメリット
- リスクの限定:譲渡対象とする事業や資産、負債を自由に選別できるため、譲受側は簿外債務や偶発債務といった潜在的なリスクを承継せずに済みます。譲渡側も、不要な事業や負債を切り離すことができます。ただし事業譲渡の場合でも譲渡条件によっては、偶発債務を負担しなければならないケースもありますので、注意が必要です。
- 事業の選択と集中:譲受側は必要な事業のみを取得し、自社の既存事業とのシナジー効果を最大化できます。譲渡側は、残った事業に経営資源を集中させることができます。
- 許認可の再取得:事業譲渡の場合、許認可は原則として譲受会社で再取得が必要となります。これは一見デメリットに見えますが、譲受会社が既存の許認可を持たない場合や、譲渡会社の許認可に問題がある場合に、クリーンな状態で事業を開始できるという側面もあります。
事業譲渡のデメリット
- 手続きの煩雑さ:個別承継のため、個々の資産の移転登記、契約の巻き直し、従業員の雇用契約の再締結など、多岐にわたる手続きが必要となり、時間と手間がかかります。
- 税負担:譲渡対象となる資産には消費税が課される場合があり、不動産が含まれる場合は不動産取得税なども発生します。また、譲渡益に対して法人税または所得税が課されます。
- 競業避止義務:譲渡会社は、原則として譲渡した事業と同一の事業を一定期間行うことが制限されます。
- 取引先・従業員への影響:契約の再締結や雇用条件の見直しが必要となるため、取引先や従業員との関係構築に丁寧な対応が求められます。
株式譲渡のメリット
- 手続きの簡素性:株式の売買契約のみで完結するため、手続きが比較的簡素で、短期間で実行できることが多いです。
- 包括承継:会社そのものが承継されるため、許認可、契約、従業員の雇用関係などが原則としてそのまま引き継がれます。
- 税制優遇:譲渡側(株主)は、譲渡益に対して所得税・住民税(譲渡所得税)が課されますが、事業譲渡の法人税に比べて税率が低い場合が多いです。
株式譲渡のデメリット
- リスクの包括承継:譲受側は、会社の持つ全ての資産、負債、そして簿外債務や偶発債務といった潜在的なリスクも包括的に引き継ぐことになります。
- 不要な資産・事業の引き継ぎ:買収対象の会社が複数の事業や資産を持つ場合、譲受側は不要なものまで引き継ぐ可能性があります。
- 少数株主の存在:株式の全てを取得できない場合、少数株主の存在がその後の経営に影響を与える可能性があります。
M&A・事業譲渡でスムーズな事業承継を実現する具体的な手続き

M&Aや事業譲渡による事業承継は、計画的かつ段階的に進めることが成功の鍵となります。ここでは、具体的な手続きの流れをステップごとに詳しく解説します。
ステップ1 準備と戦略立案
事業承継を検討し始めたら、まずは自社の現状を把握し、どのような形で事業を引き継ぎたいのかという戦略を明確にすることが重要です。
事業承継の目的と方向性の明確化
なぜM&Aや事業譲渡を選ぶのか、事業を誰に、どのように引き継ぎたいのかといった目的を明確にします。後継者不在による廃業回避、事業拡大、創業者利益の確保など、目的によってその後の戦略は大きく変わります。
自社の現状分析と企業価値の概算評価
自社の強み、弱み、機会、脅威(SWOT分析)を詳細に分析し、財務状況、事業内容、顧客基盤、組織体制などを客観的に評価します。この段階で、専門家と連携し、企業価値の概算評価を行うことで、後の交渉をスムーズに進めるための基礎情報となります。
M&A専門家(FA・仲介会社)の選定と相談
M&Aや事業譲渡は専門的な知識と経験を要するため、信頼できるM&Aアドバイザー、ファイナンシャルアドバイザー(FA)、またはM&A仲介会社の選定が不可欠です。初期段階から相談し、適切なアドバイスとサポートを受けることで、手続きを円滑に進めることができます。ただしM&A仲介会社やアドバイザーの中には、手数料を受領する事だけを目的として、悪質な買い手と契約させたり、価値がない事業や問題のある事業を高値で購入させたりするケースが後を絶ちませんのでパートナー選びは非常に重要です。
信頼できるM&A仲介会社やアドバイザーの選択肢の一つに、一般財団法人 日本的M&A推進財団の第三者承継士という資格制度があります。第三者承継士に登録しているのは、税理士や社労士などの士業資格者のみです。税理士や社労士にとっては、目先の手数料よりも、事業承継の後も事業が発展・継続していく事が重要ですので、特に買い手側の利害と一致します。もちろん長くお付き合いさせて頂いた、売り手側のハッピーリタイヤは何よりも喜ばしい事ですので、売り手側の信頼を損ねるような事もあり得ません。
事業承継では、条件が折り合う相手が見つかるまでに時間がかかるケースもあり、体調不良や病気などで承継先が見つからないまま廃業せざるを得ない事にならない様に、早めにご相談する事が大切です。
ステップ2 候補先の探索とマッチング
戦略が固まったら、次に自社の事業を引き継ぐにふさわしい候補先を探し、具体的な交渉へと進むための準備を行います。
ノンネームシートの作成と開示
自社の企業名を伏せた形で、事業内容、財務状況、強みなどの概要をまとめた「ノンネームシート」を作成します。これをM&A専門家を通じて潜在的な買収候補先に開示し、関心のある企業を募ります。
秘密保持契約(NDA)の締結
ノンネームシートに関心を示した候補先に対し、より詳細な情報(企業名を含む)を開示する前に、秘密保持契約(NDA:Non-Disclosure Agreement)を締結します。これにより、自社の機密情報が外部に漏れるリスクを防ぎます。秘密保持契約書は、秘密情報の範囲や開示が可能な範囲、秘密保持の義務期間等について、作成者によって内容が異なりますので、不利な条項が無いかよく確認する必要があります。
トップ面談と意向表明書の受領
NDA締結後、買収候補先の経営者と直接面談(トップ面談)を行い、お互いの経営理念や事業に対する考え方を共有します。相互理解が深まり、買収候補先がM&Aに前向きな場合、具体的な買収条件や意向を記した「意向表明書(LOI:Letter of Intent)」が提示されます。
ステップ3 基本合意からデューデリジェンス
意向表明書の内容に合意が得られたら、次の段階として、より詳細な調査と条件交渉に入ります。
基本合意書の締結
意向表明書の内容を基に、譲渡価格の目安、M&Aスキーム、今後のスケジュール、デューデリジェンスの範囲などを定めた「基本合意書」を締結します。この段階では法的拘束力を持たない条項が多いですが、今後の交渉の方向性を確認する重要なステップです。
デューデリジェンス(買収監査)の実施
基本合意後、買収候補先は、譲渡対象企業の事業内容、財務状況、法務、税務、人事、ITシステムなどを詳細に調査する「デューデリジェンス(DD)」を実施します。売り手企業は、この調査に対し、必要な資料を正確に開示し、質問に誠実に回答する義務があります。このプロセスには、公認会計士、弁護士、税理士などの専門家が関与します。
デューデリジェンスは、譲渡対象企業の実態を把握するために買い手が任意で行うものですが、詳細に行うほど費用も多くかかりますので、状況に応じて必要な範囲に限って実施したり、省略したりする事も可能です。また買い手側が、譲渡対象企業の事業をゼロから理解するため、売り手側にとっては、非常に細かい内容の質問と感じる内容もあります。経理担当者や税理士と連携して社長の負担を減らしていく事も大切です。
最終条件交渉
デューデリジェンスの結果を踏まえ、譲渡価格やその他の契約条件について最終的な交渉が行われます。デューデリジェンスで新たなリスクや課題が発見された場合、価格や契約内容が見直されることがあります。
ステップ4 最終契約とクロージング
デューデリジェンスと最終条件交渉を経て、両者が合意に至れば、いよいよ最終的な契約締結と事業の引き渡しが行われます。
最終契約書の作成と締結
交渉で合意された内容を盛り込んだ「最終契約書」を作成します。事業譲渡の場合は「事業譲渡契約書」、株式譲渡の場合は「株式譲渡契約書」など、M&Aスキームに応じた契約書が締結されます。契約書には、譲渡対価、支払い方法、表明保証、補償条項、解除条件などが詳細に明記されます。
クロージング(決済と引き渡し)
最終契約書に定められた条件がすべて満たされたことを確認し、譲渡対価の支払い、株式や事業用資産の引き渡し、役員交代、各種登記変更などが行われます。この一連の手続きを「クロージング」と呼び、法的にM&Aが完了する日となります。
関係者への情報開示と説明
クロージング後、従業員、顧客、取引先、金融機関などの関係者に対し、M&Aが完了したことを正式に開示し、今後の事業運営方針や体制について丁寧に説明します。特に重要な取引先や従業員への配慮は、事業承継後の安定した運営のために極めて重要です。重要な取引先や金融機関、役員や従業員などの関係者に、事業承継のどの段階で開示するのかは極めて重要です。アドバイザーと相談して慎重に行いましょう。
ステップ5 統合プロセス PMI
M&Aや事業譲渡は、契約締結がゴールではありません。買収後の統合プロセス(PMI:Post Merger Integration)を成功させることが、事業承継の真の成功につながります。
PMI計画の策定と実行
PMIは、組織、人事、システム、業務プロセス、企業文化など、多岐にわたる統合を計画的に進めるプロセスです。クロージング前から計画を策定し、統合チームを立ち上げて実行に移します。シナジー効果の最大化と、事業価値の向上を目指します。
組織・人事制度の統合と従業員のケア
両社の組織体制を統合し、人事制度や評価体系を調整します。従業員のモチベーション維持と不安解消のため、丁寧なコミュニケーションと適切なケアが不可欠です。新たな企業文化の醸成にも努めます。
業務プロセス・システムの統合
重複する業務や非効率なプロセスを見直し、統合された事業体として最適な業務フローを構築します。情報システムやITインフラの統合も重要な課題であり、スムーズな移行計画が必要です。
顧客・取引先との関係構築
M&A後も既存の顧客や取引先との良好な関係を維持・発展させることが重要です。変更点やメリットを丁寧に説明し、信頼関係を再構築するための積極的なアプローチが求められます。
M&A・事業譲渡を成功に導く秘訣と戦略

企業価値を最大化する準備
M&Aや事業譲渡を成功させるためには、売却側が自社の企業価値を最大限に高めるための準備が不可欠です。企業価値は売却価格に直結するため、買い手にとって魅力的な企業であることを示す必要があります。
まず、財務状況を徹底的に整理し、透明性を確保することが重要です。具体的には、過去数年分の決算書、試算表、税務申告書、資金繰り表などを正確に準備し、不明瞭な会計処理がないか確認します。不採算事業や遊休資産がある場合は、事前に整理することで財務状況を改善し、企業価値向上に繋がります。
次に、財務情報だけでなく、非財務情報も整理し、自社の強みや将来性を明確にアピールできるように準備します。事業計画書、組織図、主要顧客リスト、主要契約書、許認可証、知的財産権関連資料などを体系的にまとめ、事業の優位性や成長戦略を具体的に示せるようにします。特に、独自の技術やノウハウ、ブランド力、安定した顧客基盤などは、企業価値を大きく左右する要素となります。
また、M&Aアドバイザー、公認会計士、税理士、弁護士といった専門家を早期に活用し、客観的な視点から企業価値評価(バリュエーション)を実施してもらうことも重要です。これにより、適正な売却価格の目安を把握し、交渉に臨む上での基準を明確にすることができます。
交渉を有利に進めるポイント
M&Aや事業譲渡における交渉は、売却側と買収側の双方が納得できる条件を見出す重要なプロセスです。交渉を有利に進めるためには、事前の戦略立案と実行が鍵となります。
まず、自社にとって譲れない条件(最低売却価格、従業員の雇用維持、事業の継続性、代表者の引継ぎ期間など)を明確に設定しておくことが重要です。これにより、交渉中にブレることなく、一貫した姿勢で臨むことができます。
次に、複数の候補先と並行して交渉を進められる場合は、競争原理を働かせ、より良い条件を引き出す可能性を高められます。ただし、情報開示の範囲やタイミングには細心の注意を払い、秘密保持契約(NDA)を締結した上で進める必要があります。
交渉の場では、M&Aアドバイザーや弁護士などの専門家を同席させることが有効です。専門家は法務・税務・財務の観点から助言を行い、売却側の立場を代弁することで、感情的にならず冷静かつ戦略的に交渉を進めることができます。また、買収側の提案に対しては、その背景や意図を深く理解しようと努め、柔軟な姿勢で対話を進めることも大切です。
最終的な合意に至るためには、売却側と買収側の双方がWin-Winの関係を築けるような着地点を探ることが理想的です。そのためには、相手の目的や懸念事項にも配慮し、誠実な姿勢で信頼関係を構築しながら交渉を進めることが成功への近道となります。
従業員と顧客への丁寧な対応
M&Aや事業譲渡は、従業員や顧客といったステークホルダーに大きな影響を与えるため、その対応は成功の鍵を握ります。特に、情報開示のタイミングと方法には細心の注意が必要です。
従業員に対しては、M&Aの事実が決定されるまで秘密保持を徹底し、情報漏洩を防ぐことが重要です。正式な合意がなされた後、適切なタイミングで経営者自身が直接説明を行い、M&Aの目的、買収後の会社のビジョン、雇用条件の維持、待遇面での変更点などを明確に伝える必要があります。従業員の不安を払拭し、モチベーションを維持するためには、誠実かつ丁寧な対話を通じて、彼らの意見や懸念に耳を傾ける姿勢が不可欠です。キーパーソンとなる幹部社員や優秀な人材に対しては、個別の面談を通じて、引き続き会社に貢献してもらうためのインセンティブやキャリアパスを示すことも検討すべきです。
顧客や主要取引先に対しても、事業譲渡の事実を適切に伝える必要があります。サービスや製品の提供体制、品質、担当者の変更の有無など、顧客が最も懸念する点を事前に整理し、丁寧な説明を行います。事業の継続性や、M&Aによってサービスがさらに向上する可能性などを伝えることで、顧客の信頼を維持し、離反を防ぐことができます。場合によっては、買収側と共同で顧客訪問を行い、新しい体制へのスムーズな移行を促すことも有効です。
これらのステークホルダーへの丁寧な対応は、事業譲渡後の事業運営を円滑にし、企業価値を維持・向上させる上で極めて重要な要素となります。
税務・法務リスクの管理と対策
M&Aや事業譲渡は、税務および法務面で複雑なリスクを伴います。これらのリスクを適切に管理し、対策を講じることは、予期せぬトラブルやコスト発生を防ぎ、M&Aを成功に導く上で不可欠です。
税務面では、M&Aスキーム(株式譲渡、事業譲渡など)によって課税関係が大きく異なります。事業譲渡の場合、譲渡対象となる資産ごとに消費税が課税される可能性があるほか、譲渡益に対して法人税や所得税が発生します。繰越欠損金の扱い、不動産取得税、登録免許税なども考慮に入れる必要があります。買収側にとっても、のれんの償却や減価償却費の計上など、税務上のメリット・デメリットが存在します。これらの税務影響を事前に正確に把握するためには、税理士による税務デューデリジェンス(税務調査)と、具体的なスキームごとの税務シミュレーションが不可欠です。
法務面では、多岐にわたるリスクが存在します。まず、事業譲渡契約書や株式譲渡契約書などのM&A関連契約書の内容に不備がないか、弁護士によるリーガルチェックが必要です。また、譲渡対象となる事業に関連する許認可が適切に承継されるか、第三者との契約(賃貸借契約、業務委託契約、ライセンス契約など)にチェンジオブコントロール条項(COC条項)が含まれていないかを確認し、必要に応じて承諾を得る必要があります。
さらに、従業員の雇用契約の承継、知的財産権の移転、過去の訴訟リスクや係争案件の有無、環境規制への対応状況、独占禁止法上の問題なども詳細に調査し、潜在的なリスクを洗い出します。これらの法務リスクに対しては、弁護士によるリーガルデューデリジェンス(法務調査)を実施し、契約書における表明保証や補償条項を適切に設定することで、売却側・買収側双方のリスクを軽減する対策を講じることが重要です。表明保証によって情報の正確性と真実性を示したにも関わらず、相手企業が明らかに表明保証条項に違反した場合は、相手企業の損失に見合う補償を行わなければなりませんが、違反側に補填を行う資力があるとも限りません。
そのようなリスクを回避するために表明保証保険があります。場合によっては、表明保証保険を利用する事も検討が必要です。
専門家と連携し、これらの税務・法務リスクを早期に特定し、適切な対策を講じることで、M&Aや事業譲渡のプロセスを円滑に進め、将来的なトラブルを未然に防ぐことができます。
M&A・事業譲渡に関するよくある疑問と注意点

M&A・事業譲渡にかかる期間と費用
M&Aや事業譲渡による事業承継は、その規模や複雑さ、当事者の状況によってかかる期間と費用が大きく異なります。しかし、一般的な目安と費用の内訳を理解しておくことは、計画を立てる上で非常に重要です。
M&A・事業譲渡にかかる期間の目安
M&A・事業譲渡のプロセスは、一般的に数ヶ月から1年、あるいはそれ以上かかることもあります。これは、以下のフェーズの進捗に左右されます。
- 準備と戦略立案(1〜3ヶ月): 事業の棚卸し、企業価値評価、譲渡スキームの検討など。
- 候補先の探索とマッチング(2〜6ヶ月): 適切な買い手または売り手を探し、交渉のテーブルに着くまでの期間。事業規模や地域等によっては、何年もかかるケースもあります。
- 基本合意からデューデリジェンス(2〜4ヶ月): 基本合意の締結後、買い手側による詳細な調査(デューデリジェンス)が行われます。ここで問題が発覚すると期間が延びる可能性があります。
- 最終契約とクロージング(1〜2ヶ月): デューデリジェンスの結果を踏まえ、最終的な条件交渉と契約締結、そして実行(クロージング)に至るまで。
特に、マッチングの難易度やデューデリジェンスでの問題発覚、交渉の長期化などが期間を延ばす主な要因となります。
M&A・事業譲渡にかかる費用の内訳
M&A・事業譲渡にかかる費用は、主に専門家への報酬が中心となります。売り手と買い手、双方で発生する費用があります。
- M&Aアドバイザー/仲介手数料: M&A仲介会社やファイナンシャルアドバイザー(FA)に支払う報酬です。成功報酬型が一般的で、譲渡対価に応じて「レーマン方式」という料率テーブルに基づいて算出されることが多いです。着手金や中間金が発生する場合もあります。
- デューデリジェンス費用: 買い手側が負担することが多く、弁護士(法務DD)、公認会計士・税理士(財務・税務DD)、コンサルタント(事業DD)など、各分野の専門家に支払う費用です。調査範囲や企業の規模によって数十万円から数百万円以上と幅があります。
- 契約書作成費用: 弁護士に最終契約書などの作成・レビューを依頼する費用です。
- 税金: 事業譲渡の場合、譲渡益に対して法人税や所得税、消費税などが課税されることがあります。また、不動産や車両などの資産を譲渡する場合には、登録免許税や不動産取得税などが別途発生することもあります。
- その他: 企業価値評価費用、登記費用、コンサルティング費用などが挙げられます。
これらの費用は、取引の規模や複雑さ、依頼する専門家によって大きく変動するため、事前に見積もりを取り、計画に含めることが重要です。
秘密保持契約 NDAの重要性
M&Aや事業譲渡の初期段階では、企業の機密情報が多数開示されることになります。この情報漏洩のリスクから双方を守るために、秘密保持契約(NDA: Non-Disclosure Agreement)の締結は不可欠です。
秘密保持契約(NDA)とは
秘密保持契約は、M&A・事業譲渡の検討過程で開示される企業秘密やノウハウ、財務情報、顧客情報などの機密情報を、相手方が目的外に使用したり、第三者に開示したりすることを禁じる法的拘束力のある契約です。一般的に、M&Aの交渉が本格化する前の段階で、情報開示に先立って締結されます。
NDAが重要な理由
- 情報漏洩リスクの防止: 財務状況、顧客リスト、技術情報など、企業にとって極めて重要な情報が外部に漏れることを防ぎます。情報漏洩は企業価値の毀損や競争力の低下に直結します。噂が流れて、顧客離れや従業員の離職を招かない様にする事が大切です。
- 交渉の円滑化: 売り手側はNDAがあることで安心して情報を開示でき、買い手側は必要な情報を得て検討を進めることができます。これにより、交渉がスムーズに進行します。
- 企業価値の保護: 万が一、交渉が不成立に終わった場合でも、開示された情報が不当に利用されることを防ぎ、企業の利益と価値を守ります。
- 法的措置の根拠: NDAに違反があった場合、損害賠償請求などの法的措置を講じるための根拠となります。
NDAに盛り込むべき主な内容
- 秘密情報の定義: どのような情報が秘密情報に該当するのかを具体的に明記します。
- 秘密保持義務の範囲: 秘密情報の使用目的、開示範囲(役員、従業員、アドバイザーなど)、開示先を限定します。
- 秘密保持義務の期間: NDAの効力が及ぶ期間を定めます。交渉終了後も一定期間は義務が継続するのが一般的です。
- 返還・廃棄義務: 交渉が不成立に終わった場合や期間満了時に、開示された秘密情報を返還または廃棄する義務を定めます。
- 違反時の措置: 秘密保持義務に違反した場合の損害賠償責任や差止請求権などを定めます。
NDAは、M&A・事業譲渡を安全かつ円滑に進めるための最初の重要なステップです。専門家である弁護士に相談し、自社の状況に合わせた適切な契約内容を作成することが強く推奨されます。
M&A後のトラブルを避けるために
M&Aや事業譲渡は、契約締結がゴールではありません。その後の統合プロセス(PMI: Post Merger Integration)や、予期せぬ問題の発生によって、期待したシナジー効果が得られなかったり、深刻なトラブルに発展したりするケースも少なくありません。M&A後のトラブルを未然に防ぎ、成功に導くためには、事前の準備と対策が不可欠です。
M&A後に発生しうる主なトラブル
- PMIの失敗: 企業文化の違い、人事制度の統合の難しさ、ITシステムの連携不備などにより、従業員のモチベーション低下や離職、業務効率の悪化を招くことがあります。
- 簿外債務・偶発債務の発覚: デューデリジェンスで見抜けなかった過去の債務や、将来発生しうる偶発的な債務がM&A後に発覚し、買い手側の負担となることがあります。
- 契約不適合責任(旧:瑕疵担保責任)に関する問題: 譲渡された事業や資産に契約内容と異なる点(品質、数量、種類など)が発覚した場合、売り手側の責任が問われることがあります。
- 主要な従業員や顧客の離反: M&Aによって組織体制や方針が変わり、重要な人材が流出したり、顧客が他社に乗り換えたりするリスクがあります。
- 競業避止義務違反: 売り手側がM&A後に類似の事業を開始し、買い手側の事業に影響を与えるケースです。
- 税務上の問題: M&A後の税務処理や、繰越欠損金の利用制限など、税務上のリスクが顕在化することがあります。
- 経営者保証の問題: 借入金に経営者保証がある場合に、契約条件にあるにもかかわらず、譲受側が事業譲渡後に売り手側の経営者保証を外さないなど、契約内容の不履行をされる事例もあります。
- M&Aを隠れ蓑にした財産狙いの問題: 事業の承継を目的とした買収ではなく、買い手が売り手の預金や不動産などの資産のみを目的とし、資産のみを処分して事業を放置して夜逃げしてしまう事例もあります。
トラブルを避けるための対策
- 徹底したデューデリジェンスの実施: 買い手側は、法務、財務、税務、事業、人事、ITなど、あらゆる側面から対象企業を詳細に調査することが不可欠です。専門家を起用し、潜在的なリスクを洗い出しましょう。売り手側も、事前に自社の状況を把握し、開示情報を整理しておくことが重要です。
- 明確な最終契約書の作成:
- 表明保証条項: 売り手側が、対象企業の財務状況や法的側面などについて事実を表明し、それが真実であることを保証する条項です。
- 補償条項: 表明保証に違反があった場合や、特定の偶発債務が発覚した場合に、売り手側が買い手側に損害を補償する範囲や条件を明確にします。
- 競業避止義務: 売り手側がM&A後に一定期間、同種事業を行わないよう義務付ける条項です。
- PMIに関する取り決め: 統合の具体的な計画や、引き継ぎに関する協力義務などを契約書に盛り込むことも有効です。
- これらの条項を弁護士と綿密に協議し、リスクヘッジを図ることが重要です。
- PMI(統合プロセス)の周到な計画と実行: M&A成立前から統合計画を策定し、組織文化、人事制度、ITシステム、業務プロセスなどの統合を段階的に進めます。特に、従業員への丁寧な説明とコミュニケーション、エンゲージメントの維持が成功の鍵となります。
- 専門家との継続的な連携: M&Aアドバイザー、弁護士、公認会計士、税理士など、各分野の専門家とは契約締結後も密に連携を取り、予期せぬ問題が発生した際に迅速に対応できる体制を整えておくことが賢明です。
- 従業員と顧客への丁寧な対応: M&Aの情報を開示するタイミングや方法を慎重に検討し、従業員や顧客の不安を解消するよう努めます。特に、主要な人材や顧客が離反しないよう、きめ細やかな配慮が必要です。
M&A後のトラブルを避けるためには、契約前の徹底した調査と契約内容の明確化、そしてM&A後の統合プロセスを計画的に実行することが不可欠です。これらを怠ると、せっかくのM&Aが「負の遺産」となりかねません。M&Aはほとんどの事業者にとって初めてで、分からない事ばかりかもしれませんが、仲介業者やアドバイザーに任せきりにしない事や、信頼できるパートナーを選ぶ事も重要です。
まとめ

日本の経営者の平均年齢は60歳を超えているにも関わらず、後継者が不在の企業が過半数を超えています。
M&Aや事業譲渡は、後継者不在などの課題を抱える中小企業の事業承継において、事業の継続と発展、そして従業員の雇用を守るための強力な選択肢となります。親族内承継や従業員承継が困難な場合でも、外部の資本やノウハウを取り入れることで、企業価値を最大化し、新たな成長機会を創出することが可能です。
M&Aや事業譲渡の成功には、周到な準備、信頼できる専門家との連携、そして丁寧な手続きが不可欠です。本記事で解説した具体的なステップと成功の秘訣を実践することで、一人でも多くの経営者が、貴社にとって最適な形でスムーズな事業承継を実現し、企業の未来を確かなものにできる事を願っております。より詳しく聞きたい事や自社の場合にはどうしたらよいか疑問に思われた場合は、YFPクレア 神田支店にお気軽にご相談ください。





